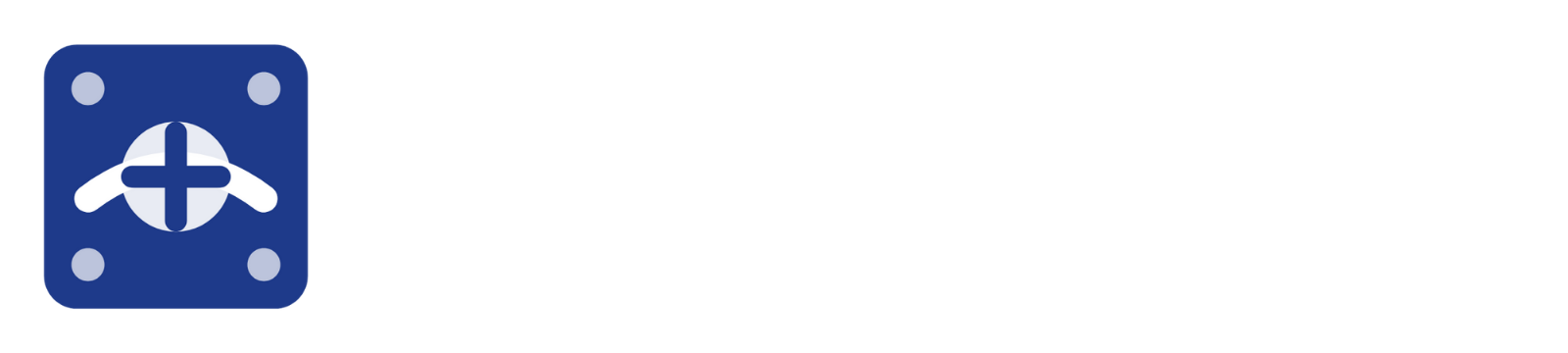24時間受付中
マンジャロ中止後はリバウンドする?最新エビデンスと対策
マンジャロ中止後はリバウンドする?最新エビデンスと対策
マンジャロ(チルゼパチド)を中止すると体重は戻りやすいことが多くの臨床試験で示されています。大規模試験(SURMOUNT-4)では、36週間の治療で平均20.9%減量した後、中止した群は1年で約14%増加し、減量分の約2/3が戻る結果となりました。一方で治療を継続した群は、さらに5%以上の追加減量を達成しています。つまり、肥満症は慢性疾患であり、薬をやめると体は「元の体重に戻ろう」と働いてしまうのです。
中止後に体重はどれくらい戻るのか
SURMOUNT-4試験の結果は、リバウンドの現実を端的に示しています。36週間のマンジャロ治療で大幅な減量を得られた後、中止すると1年間で体重の2/3が再増加。一方、治療を続けた群では体重がさらに減少し、長期的な維持の重要性が浮き彫りになりました。
また、他のGLP-1薬でも似た傾向が確認されています。オゼンピック/ウゴービ(セマグルチド)のSTEP試験延長では、中止後1年で失った体重の約2/3が戻りました。サクセンダ(リラグルチド)ではリバウンド幅はやや小さいものの、やはり体重は元に戻る方向に進みます。
リバウンドが起こる仕組み
ホルモンと食欲の反動
マンジャロはGLP-1とGIPに作用し、脳の満腹中枢に働きかけます。中止するとこの効果が消え、食欲が一気に戻ります。さらに減量に伴い、グレリン(食欲ホルモン)が上昇し、レプチン(満腹ホルモン)は低下。強い空腹感が襲ってくるのは生理的な反応です。
代謝の低下
体重が減ると基礎代謝が落ち、同じ生活でも消費カロリーが減ります。特に急激な減量では筋肉量も減り、さらに代謝が低下。余分なカロリーが脂肪に蓄積しやすくなります。
行動習慣の後戻り
治療中は「薬が食欲を抑えてくれる」ため努力せずに痩せやすいですが、中止するとブレーキが外れ、以前の食習慣や過食のクセが戻ってきます。
他のGLP-1薬との比較
- オゼンピック/ウゴービ(セマグルチド):減量効果は15%前後と大きいが、中止後は急速に戻る傾向あり。
- サクセンダ(リラグルチド):減量効果は5〜8%と中程度。中止後の増加は比較的緩やかだが、長期的には戻る方向。
共通点:新しい薬ほど減量効果は大きいが、リバウンドも目立ちやすい。肥満症治療薬に「中止後も維持できる魔法の薬」は存在しません。
リバウンドを防ぐ3つの方法
徐々に減薬することで、ホルモンと代謝の反動を和らげられます。
当院でも、テーパーによってリバウンドを防ぎながら体重を維持できている患者様が多くいらっしゃいます。
- 高タンパク+野菜中心の食事
- 糖質は「質と量」を調整し、白米や砂糖は控えめに
- 週2〜3回の筋トレ+有酸素運動で筋肉を維持
中止後も定期的に診察・体重測定を行い、必要に応じて薬を再開・変更します。
当院での傾向と患者様の声
当院では、マンジャロを中止した後もテーパー+生活習慣改善を並行することで維持できている患者様が多いというデータがあります。
- 「徐々に減薬しながら、タンパク質中心の食事に変えたら体重を維持できている」
- 「運動習慣を取り入れたことで、薬を減らしても体重が戻らなかった」
- 「完全にやめたら少し戻ったが、再開してまた安定した」
こうした声からも、リバウンドを恐れすぎず「中止後のプラン」を持つことが重要だと分かります。
よくある質問(FAQ)
Q. いつから減薬を始めればいいですか?
Q. 減薬はどのくらいの期間をかけますか?
Q. リバウンドしてしまったら?
エビデンスに基づく見解
肥満は慢性疾患であり、糖尿病や高血圧と同じように「治療をやめれば戻る」のは自然なことです。薬は効果がある間こそ価値があり、長期的な使用も一つの選択肢です。ただし副作用や費用面もあるため、無理なく継続できる方法を主治医と一緒に考えることが推奨されます。
まとめ
- マンジャロ中止後は体重が戻りやすい
- 理由はホルモン反動・代謝低下・生活習慣の後戻り
- 防ぐには段階的減薬・生活習慣の強化・定期診療が重要
- 当院の経験上、テーパーで維持できている患者様が多数
リバウンドは特別な副作用ではなく、肥満症という病気の性質そのものです。正しい知識とサポートがあれば、体重を維持することは可能です。
※ 記事内容は医療情報であり、個別の診断ではありません。治療方針は医師とご相談ください。